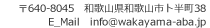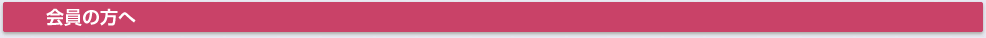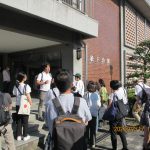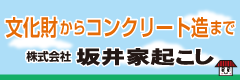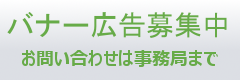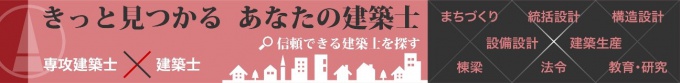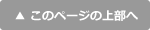委員会・支部活動報告
和歌山大学松下会館DOCOMOMO Japan認定記念講演会 報告
和歌山大学松下会館(1961年竣工・渡辺建築事務所(渡辺節)設計・竹中工務店 施工) DOCOMOMO Japan「日本におけるモダン・ムーブメント」建築認定記念講演
鉄筋コンクリート2階建で、ファサード(正面)に穴あきブロックを使うなどのデザインが特徴的の和歌山大学松下会館(和歌山市西高松)が「日本におけるモダン・ムーブメント」(No 270)建築に県内で初めて選定された。
7月17日に行われた松下会館前の贈呈式では、「DOCOMOMO」(ドコモモ)の日本支部「DOCOMOMO Japan」(ドコモモジャパン)前理事で、京都工芸繊維大学助教の笠原一人さんが、和歌山大学の本山貢学長に選定プレートを手渡された。(これまでに国内264件の建築物が選定されていて、2022年度は、松下会館を含む16件が新たに選ばれ、計280件となった。)贈呈式後に同館隣の県立図書館2階で開催された記念講演会には約80名の方が集まり、本山学長から「松下会館は歴史と文化の拠点そして県内11の高等教育機関の拠点、更には、市民の皆さんの力を借り、この松下会館をもう一度活性化させていくのが、われわれの使命。次世代の教育を担う、その継承と保全をしっかりと担っていきたい」との挨拶があった。
講演会では、笠原助教から「文化遺産としての松下会館」をテーマに、会館の特徴として「柱や梁を強調し、モダニズム建築の一つだが、古風な様式性を随所に見いだすことができ、様式性とモダン性が共存し、渡辺節独自のモダニズムの在り方を示している。建物だけでなくドアのノブや階段の手すりまで総合的にデザインされている」と説明があった。
続いて、髙砂正弘和歌山大学名誉教授が「松下会館の魅力」と題して、「今回は和歌山大学での教育と大学に来る前に設計していた時に大阪建築コンクールで渡辺節賞を受賞したご縁で講師によばれたと考えている。特に渡辺節事務所の図面の特徴として、矩計図が1/50で書かれている。高さ関係がいっきに見える。断面図、平面図を一つの図面に書いて、それで建物がどんな感じに見えるのかが気になることからそのような書き方になったと考えられる。」と話され昭和初期にモダニズム建築を代表する建築家として活躍された安井武雄と比べて、「渡辺節は様式コテコテ建築をつくっている。合理主義といわれているが実は自由主義ではなかったのか。アトリエの人であり建築家として次世代の建築家を育てている。」との説明があった。
意見交換では、「松下幸之助さんが寄付した建物を「松下遺産」ネットワークとして連携して保全活用していけばどうか。」「地域での生涯学習の場」「教員の交流と小学校中学校高校大学の連携の場としての活用」「子どもの育ちの場」「松下会館の管理は和歌山大学で維持費については地域の人の協力も必要」「松下会館の建物だけでなく緑も大切だ」「松下会館があ
ることで和歌山大学との連携が出来る」等の提案があった。
また、「保全活用に改修は必要だが何が大切か。」との質問について、「改修は避けられないので、特徴を確認してそれを中心に残していく(尊重して引き延ばしていく)ことが大切、大和張りの天井が奥まで残っているのは良かった。」との話があった。
講演会終了後、参加者は2つのグループに分かれて松下会館と松下会館の図面の見学が行われ、三角窓、舞台下の通気口デザインや大和張りの天井に関心が寄せられていた。
参加者からのメッセージ
〇松下会館の今後の保存や活用について、ご意見があればお聞かせください。
| 高野山大学内の図書館や松下講堂などとの建築ツーリズムなどいか
(高野山見学からたちより、50代、ヘリテージマネージャー, 日本建築学会, DOCOMOMO Japan) |
| 学生が利用するように高松周辺の研究を行う。その関係でさまざまな分野の講義を実施する。一度でも利用するとそういうところがあるのだと和大生も認識できると思う。現状では他府県出身者はもちろんのこと、和歌山市内出身者でもほとんど知らないと思う。 また高校生からの認知を上げるために自習室を設置する。さらに、大学について大学生が発信するところを常時でなくともおいていると高校生と和大生のつながりが生まれるのではないか。また一般向けイベントを企画して、ボランティアを呼び込むか、バイトとして松下会館に来るようにする。とにかく松下会館に対する学生の認知をまずは上げる必要があると思う。(和歌山市内、20代、和歌山大学生, 「国宝」和歌山城木造復建の会) |
| 幼、小、中、高、大学、特別支援学校が連携した取り組み。また地域連携の取り組み。(和歌山市内、40代、和歌山大学生, 高松小学校職員) |
| まず、和歌山の建築文化遺産として、市民の関心をもっと普通に醸成できるような工夫をしてください。知る、発見する、体感する、などから好奇心を育ててください。(70代) |
| 価値ある大切な建物であるからこそ広く一般の人に利用してもらい認知度を上がる。一般市民が(も)ゆっくりくつろげる場→飲食を伴う(利益を得る)施設を希望、多くの人々へ建築への興味を助長、和歌山大学が許すのなら、県立図書館との連携によりコミュニティカフェ、パン、ケーキ(海南市、60代、和歌山県建築士会) |
| 本日の笠原先生の熱心なご講演ありがとうございました。そして和大の先生方」、和工の先生からの予定外のご苦労話等も良かったです。モダン、ムーブメント建築認定和歌山第一号おめでとう㊗️🎊ございます。^_^国宝や有形文化財のように、魅力のある建築物を残していけるように、和歌山県も、もっととりくんでほしいと思いました。 |
〇松下会館について、5年前にも講演会を開催し、この建築を広く知っていただき、保存活用につながる取り組みを行ってきました。建築士会の今後の活動や取り組みについて、ご意見があればお聞かせください。
| 小学校と建築士会学校連携した取り組み。(和歌山市内、40代、和歌山大学生, 高松小学校職員) |
| 何年か前に、やはり、県立図書館で松下会館が、取り壊されるかもしれないというお話を聞きました。その時もったいないと私も思いましたが、私自身何も活動できなかったなあ、、と反省しています。今回、建築士会の皆様や、和大本山学長のご尽力のお陰で、残されてことは、本当にありがたい事です。 これを機会に是非、お年寄りにも、障がいのある方達にも、みんなに、より良い開かれた有効な活用の仕方を是非と願っております。本年度はヘリテージ研修会が、ないとのこと、残念です。来年度は、是非又、研修の場を設けて下さい。宜しくお願い致します🥺 |
和歌山市支部事業委員長 高垣晴夫
「海鼠壁の武家屋敷・旧和歌山藩士大村弥兵衛長屋門」講演会報告
「海鼠壁の武家屋敷・旧和歌山藩士大村弥兵衛長屋門」講演会報告
日時/7月5日(日)13:30~15:40
場所/和歌山県立近代美術館(和歌山市)
参加/会員・一般参加者を含め約80人
第1部 「武家屋敷門長屋旧大村弥兵衛屋敷」の上映
歴史的建造物映像化の会 代表 中西重裕(本会副会長)
第2部 なまこ壁の武家屋敷・旧和歌山藩士大村弥兵衛長屋門
文化財建造物保存修理技術者 鳴海祥博
旧大村家住宅長屋門は、県庁の北、有田屋町にあった大村家住宅を明治期に堀止東に移築し利用されていたもので、紀州徳川時代の貴重な武家屋敷の遺構です。移築により戦災を免れましたが、江戸期のオリジナルではなくなったことから文化財としては低く評価されてき
ました。解体が決まったことから、歴史的建造物映像会のから所有者に記録保存を要望し、所有者の承諾を得て記録が行われましたが、この記録活動の報道をきっかけに県の支援を得て、一転、保存されることとなったものです。建築士会では支部活動や会員個人の活動として、これまでいくつかの建物の解体に先立ち、見学会や記録保存を行ってきましたが、今回は建築士の活動が保存に結びついた貴重な事例となりました。
このような経過から、本講演会では、保存のきっかけとなった歴史的建造物映像化の会による「武家屋敷門長屋 旧大村弥兵衛屋敷」の上映と、移築プロジェクトの技術監修をされている元和歌山県文化財センターの鳴海祥博さんにご講演いただき、解体調査で明
らかになったこの建物の歩んできた経過、文化財や地域資源としての価値について解説をいただくとともに、鳴海さんがいままでに手がけてこられた経験から文化財
保存がなぜ必要なのかとについてご講演をいただきました。また、会場には図面や海鼠壁に使う平瓦、屋根瓦、また、和歌山市支部事業委員会で調査を実施、保存活動を行っている貴志邸の資料を会場に展示しました。
講演では、この門長屋の来歴、門長屋という建築物の機能、和歌山城周辺のまちなみ(戦前このような長屋門が立ち並ぶ武家屋敷町が形成されていた)、海鼠壁の機能と歴史について説明がありました。門長屋は武家の格を表す門の機能と武家に求められる戦時の兵力となる家臣の住居の機能を兼ねたもので、石高により門の構成も変わることが紹介されました。また、海鼠壁については明暦の大火以降、幕府が進めた延焼防止のための防火構造で、全国的にも残っていることが貴重な状況であることが報告されています。
今回の講演会では
1)文化財指定されていないが、歴史的価値のある建造物はたくさん存在する
2)歴史的建造物が残るためには建築士等地域の人が声をあげる
3)見つかった歴史的建造物を保存していくためのしくみづくり
といったことが必要ではないかとするまとめを行い、閉会しました。
和歌山市支部 明石和也