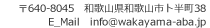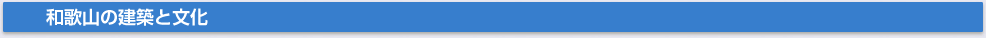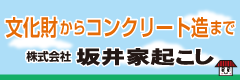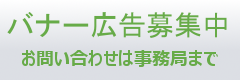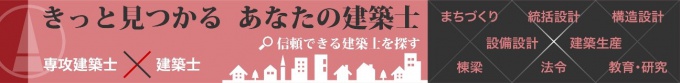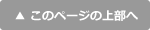旧制粉河高等女学校同窓会館(粉河高等学校同窓会館)
旧制粉河高等女学校同窓会館(粉河高等学校同窓会館)
【建築概要】
■所 在 地 紀の川市粉河
■構造・規模 木造2階建一部平家建 瓦葺及びスレート葺
■建築 面積 359㎡
■和歌山県 登録有形文化財(建造物) 登録年月日:2023年8月7日
今回は「旧制粉河高等女学校同窓会館(粉河高等学校同窓会館)」を紹介します。
紀の川市粉河の市街地東の高台にあり、大正2年(1913年)創立の旧制粉河高等女学校(県立の女学校)の開校20周年を記念して、昭和9年(1934年)に同窓会館として建設されました。工事監督は和歌山県技手の福田健三氏が、和歌山市の山田榮次郎氏が施工されたそうです。敷地の中央東寄りに鉄筋コンクリート造の校舎に囲まれて建ち、女学校時代から残る唯一の建造物です。
同窓会館は学校行事や同窓会の集いの場のほか、かつては女学生が1週間ほど泊まり込み、炊事や掃除・接遇等の実習を行う家庭実習寮としても使用されたそうです。
建築面積は359㎡で、建設当初より、赤い洋瓦葺の大屋根をもつ洋館2階建の「西棟部」に和館のスレート葺き切妻2階建(一部平家建)の「中央部」と宝形平家造の「東棟部」が連なって建っていて、現在もその構成を残しています。昭和38年(1963年)に西棟部の1階を生徒ホールに改修し、昭和60年(1985年)には外壁を改め、窓等をサッシ化し、令和4年(2022年)には屋根の葺き替え、耐震補強、便所・シャワー室増設をする一方で、改造されていた玄関ホールの階段や応接室の内装を現すなど一部を復元されたそうです。
- 西棟1階元応接室
- 西棟1階ホールの見返し
- 西棟2階西広縁
- 南西より見た全景
西棟部は洋風建築、外壁を白い大壁とし縦長の上げ下げ窓を連続して並べ、優雅で重厚なデザインが特徴で急勾配の屋根は3棟の中で一番大きい棟高12.9mにも達します。1階は南面に玄関、大きな生徒ホール、2階に上がる階段、旧応接間があります。生徒ホールはかつて南北に廊下を通し、廊下の東側には洋室の食堂、西側には風呂等が設けられていました。内装は大壁漆喰塗で、応接室や食堂には腰板が貼られていたそうです。2階には三方に広縁が設けられ、南北に続き間座敷、畳敷に竿縁天井、真壁造の和室があります。外周には上げ下げ窓が連続して並べられて洋風の外観なのに、広縁を挟んで天井が高くとられた和風の大広間が広がっており、独特の空間を演出していました。小屋組構造は勾配をきつく構えたキングポストテラス組になっているそうです。
中央部は真壁造の和風を基調とした外観で、1階はセミナールームとして使用していますが、かつては広縁を備えた和室を東西に三室あり、生徒の宿泊に用いられていました。2階は西棟部の2階から入ることができ、和室を二室並べ、畳敷きに竿縁天井とし、東の主室には床の間を備えてあります。
東棟部は中央部同様和風を基調とした外観ですが、応接間のある南西部大壁に上げ下げ窓を並べる洋風の外観になっています。中央部との取合いとなる西側に玄関を置き、南側に続き間座敷、北側は便所・シャワー室に改造されていますが、かつては和室二室を並べていました。また、屋根はスレート葺きですが、屋根面の中途を錣葺きとしており特徴的です。西棟・中央・東棟部は構造上一体となったものであり、令和4年改修時の調査では、各所に筋交・火打梁・貫ボルト・頬杖金具・羽子板ボルトや鉄筋ブレス等が確認されたそうです。建設当時としては斬新な意匠だけでなく、耐震性を意識し構造的にも勘案した造りとなっていると想像できます。
現在は生徒さんに「さゆり会館」として親しまれ、1階は生徒ホール・食堂・セミナールーム、2階は琴部の活動に、また和館では囲碁・将棋部の活動に使用されています。取材当日は校長先生に敷地をめぐり、当時の校舎の跡地や地形・建物の特徴など説明して頂きました。令和4年の改修の際、調査を担当された和歌山県教育庁生涯学習局文化遺産課の御船様にも改修に至るまでの経緯や改修時の発見、建設時の時代背景等のお話を伺うことができました。建設当時はまわりに建物も少なく、紀の川や粉河の街中から見上げると高台に建つ尖り屋根の白亜の洋館は新奇で開明的な印象があったと思います。また和と洋が共存する外観は粉河のシンボル的な存在でもあり、文化財として今後も保存・活用がされることを期待したいと思います。
【会報誌きのくにR7年6月号掲載】
情報・出版委員 堀内弘樹