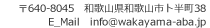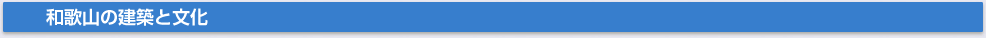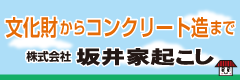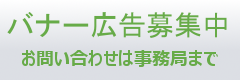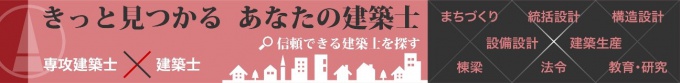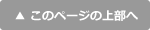田辺市立美術館
田辺市立美術館
建築概要
敷地面積 5339.76㎡
設計・監理 株式会社坂倉建築研究所 大阪事務所
施工 東急建設株式会社 和歌山営業所
建物概要
主要用途 美術館
構造規模 鉄骨造(耐火建築物)1階建て(一部ピロティ)
建築面積 1668.33㎡
延床面積 1580.93㎡
仕上げ 外壁 磁器モザイクタイル張り
横木下地羽目板張り「ジャラ」「イエローバラウ」
屋根 金属板葺き「表面処理亜鉛合金板」
工期 1993年(H5)11月~1995年(H7)3月
開館 1996年(H8)11月1日
昭和63年に亡くなられた田辺市出身の実業家、脇村禮次郎氏の「故郷の田辺市に美術館を」との遺志を引き継いだ御遺族からの株券の寄付を受けて建設計画が進められた。設計はプロポーザル方式で坂倉建築研究所の太田隆信氏らの案が採用された。太田氏も少年期に田辺の景色に魅了された人である。
平成11年に行われた南紀熊野体験博にさきがけ、シンボル会場の1つであった新庄総合公園の一角に建設された。前面道路からは木々に遮られ見えない。美術館駐車場入口に進むと横板張りで屋根頂部にガラス窓がチョコンと突出したなんとも可愛い数棟が現れ、まるでコロニー、集落のようである。正面に回ると中央はタイル張りの管理棟、左側に2棟右側に3棟の展示室棟があり連絡通路で一体化されている。外壁はジャラの横板張り、下部は袴のように張り出した亜鉛鋼板葺き裳階(もこし)で壁体内通気のダクト管が納められている。角は欠かれ上部屋根の雨水処理を兼ねたデザインである。右側棟は敷地の高低差でピロティ構造だが隅柱を中央に寄せた跳ね出し梁になっており建物が宙に浮かんでいるように見える。外壁板は耐久性を重視して敢えて南洋材を採用している。東西南面は10年前に再塗装したが北面は当時のままでありながらそんなに劣化していない。2重壁の通気工法と遮熱効果で室内環境も良好とのことである。
中央エントランスホールは屋根勾配の斜天井で最上部のトップライトから降り注ぐ光が壁面の複雑な凹凸を際立たせ開放的で豪華な空間だがフリースペースで誰でも利用することが出来、図書なども置いていて美術館の受付となっている。
展覧会は有料だが低額で学生や18歳以下は無料と破格なのは教育委員会直轄の施設ならではということなのだろう。
展示室も勾配天井で頂部のトップライトからランプのようなガラス張り部屋の下に天傘状の浮天井があり自然光を遮るような構造である。絵画は退色防止上、自然光は望ましくなく絶えず細かな調整をされ、ぼんやり天井のトップライトが見える程度の明るさで、まるで夏蜜柑の中にいるような不思議な感覚だ。各展示室は同じ面積で1面がガラスケース、他はピクチャーレールやハンガーで壁面展示され作品をLEDスポットライトで浮かび上がらせている。また古い作品は前面をアクリル板で覆い保護することで間近から鑑賞出来るよう工夫されている。最上部で7メートル近くもある勾配天井でトップライトへのアクセスは宙に浮いたガラス部屋からしか出来なく、照明器具の調整や交換もとても大変なのではないかと思われるが学芸員さん自ら美術館で所有する小型伸縮式高所作業車を操作して都度なされているとのことで感心した。左右の展示室はそれぞれ連絡通路で連結され回遊式となっていて通路の個性的な開口部からは中庭や休日には多くの子供たちで賑わう公園を見渡すように計画されているが、直射日光を避けるため普段は閉じられている。設計者がクラスター型というコロニーは将来の増築にも対応しやすく増えて成長する様は故郷を想う先人たちの軌跡であり希望でもあるだろう。
最後にお忙しいなか長時間にわたり取材対応頂いた学芸員様、関係者様に感謝申し上げます。当館は令和7年6月から開館以来30年ぶりに照明設備や空調機器の更新、施設のメンテナンスのため暫く休館となりますのでご了承ください。
【会報誌きのくにR7年4月号掲載】
情報・出版委員 永田佳久